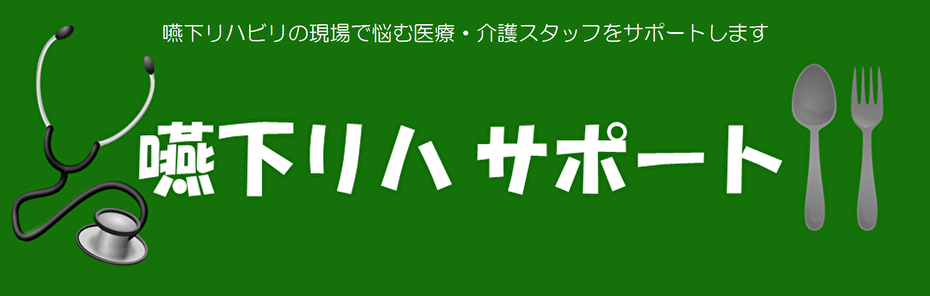知識ゼロからはじめる よくわかる嚥下評価
No more 絶食嚥下リハビリ!!

※参考図書 2025年発売の新刊
嚥下評価への意欲はあるけど全然自信がないという看護師さん、栄養士さんに、ST大野木が全12回の研修でノウハウを伝授するというストーリー仕立ての内容になっています。会話形式を取り入れながら、多職種の嚥下評価初心者の方が「そうそう!」「そこが知りたかった!」と共感しながら楽しく学べるように工夫しました。
もちろん、評価に自信を持つために必要な頸部聴診法についても、体験や動画で分かりやすく学べます。唾液やトロミ水、水などの嚥下評価のノウハウをこれだけ具体的に分かりやすく解説している本はないはず!
2025年前期 募集中
| タイトル | ➀ 知識ゼロからはじめる よくわかる嚥下評価のコツ |
| 開催日 |
2025年 4月20日(日)終了、4月27日(日) ※各回、内容は同じです |
| 時間・視聴方法 |
10時~12時(Zoomによるオンライン視聴) ※アーカイブ視聴はございません |
| 対象職種 | ST・栄養士・看護師・歯科医師・歯科衛生士・介護福祉士など |
| 講師 | 大野木宏彰(ST) |
| 主催 | 嚥下リハサポート |
| 募集人数 |
30名程度 |
| 受講料 | 4000円(税込) ※PayPalによるオンライン決済 or 銀行振込 |
講師からのメッセージ
医療・介護現場では、「食べさせたから誤嚥性肺炎になった」「食べて肺炎を繰り返したらどうするの!」という、「食べ(たから・させたから肺炎)ハラ(スメント)」が蔓延しています。
私は、口から食べることができない一番の理由は、嚥下障害の重症度よりも、この「食べハラ」にあると感じています。それに萎縮してしまうと、「摂食嚥下リハビリ」ではなく、「絶食嚥下リハビリ」が行われることになってしまうのです。
「ミールラウンドをしても自分では嚥下状態の評価ができない・・・」
「STはいないし、VFやVEはできない・・・ 嚥下の悪い方をどう判断したらいいんだろう?」
「誤嚥や窒息のリスクが判断できず、食形態の変更がいつも不安・・・」
「ゼリー食でもむせたって介護スタッフから相談された・・ どうしたらいいの?」
こんな現場の悩みに応えるべく、摂食嚥下の基礎知識から実践的な嚥下評価ポイントまでを分かりやすくまとめています。
このセミナーでは、まずは嚥下状態をシンプルかつ的確に判断できるように、「3つの嚥下機能」「6つの嚥下障害タイプ」を理解してもらいます。その後に、「3つの嚥下機能」をベッドサイドや食事場面で評価していく具体的な観察ポイントやコツについてお伝えしていきます。
評価に必要なのは、聴診器とストローやトロミ水、ゼリーなど、どこでも準備できるものだけです。食形態選択のための咀嚼機能評価は特に現場で役立つでしょう。「嚥下評価のために聴診器を買ってはみたもののタンスの肥やし状態・・・」なんて声をきくこともあるのですが、頸部聴診法もセミナー①「頸部聴診法のススメ」につながる導入編として学んでいただけます。
従来の教科書的なマニュアルから脱却し、嚥下評価のスキル向上を目指したい方は、職種限らず役立つ内容ですので気軽にご参加ください。「食べハラ」に負けない一人前の嚥下評価スキルを目につけましょう!
プログラム
1、これだけは押さえておきたい!嚥下の解剖・メカニズム
2、マニュアルの殻を破ろう!!嚥下評価はもっと簡単にできる!!
●3つの嚥下機能の判断ができればOK
●嚥下障害 6つのタイプ分類
●頸部聴診法 はじめの1歩
3、嚥下評価の進め方と使用物品
4、咽頭クリアランス評価のポイント
5、咀嚼・食塊形成~送り込み評価のポイント
6、嚥下反射のタイミング評価のポイント
7、食事姿勢や介助方法のコツ
●嚥下を見る前のチェックポイント
●食事姿勢3つの選択方法
●餅の窒息事故 男性が圧倒的に多いのはナゼ?
●頸部聴診法で通過具合を捉える
●ストロー・えびせんの咀嚼評価方法のコツ
●鼻咽腔逆流の有無はヨーグルトでチェックできる
・
・
・
など、現場ですぐに役立つ評価ポイントやコツがわかりやすく学べます。
嚥下評価にかかわるすべての職種の方へ!
備考
※セミナー時間は小休憩や質疑応答も含め2時間を予定しております
※WebセミナーQ&Aをご確認の上、お申し込みください